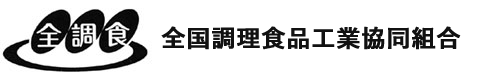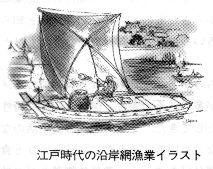みんなもぜひ 一緒に味わって、健康と幸せをつむいでね!

佃煮は、日本の食文化を代表する食品のひとつですね。シンプルでありながら、深い味わいが魅力の佃煮。食べるごとにその美味しさに気づく、まさに日本の伝統的な味です。また長期保存ができるものも多いので、常備食としてもおすすめ!
私たち「つくだに食べ隊」は、いろんな種類の佃煮を毎日食べたい!そして健康と幸せをみんなにも教えてあげたいのです。つむぎ、しぐれ、うみね、カイ、レンの5人をよろしく!


「つむぐ」という意味から、伝統の味を伝えていくことを願ってついた名前。
「つくだに食べ隊」のリーダーよ!
つむぎと仲間でつくだにを多くの人に広める活動を紡いでいきます!


しぐれ煮という佃煮の調理法からの命名。
しょうがを効かせたようなひと味違うコメントを言う娘よ!

私の推しはあさりの佃煮!甘辛いタレがあさりにしっかり染み込んで、海の香りがお口いっぱいにジュワッと広がる感じなの。低カロリーで、鉄分やミネラルも豊富なのもGOOD!あさりの食感もプリッとしてて、タレとの相性が抜群だから、何度でも手を伸ばしたくなるわよ。


波紋が重なり合う様子の「漣」からついた名前。
釣りをしながらおにぎりを食べるのが好き。

オレはわかさぎ一択だね!丸ごと一匹頬張ると、甘めの味付けとわかさぎの風味・旨味がたまらない。骨まで気にせず食べられて、カルシウムやDHAも豊富だぜい。タレと魚が絶妙なバランスで絡み合う感じとちょっと大人の味わいが、後を引いてやみつきになるんだ。


まさに海の恵みを音で伝えることからついた名前。
お弁当作りが得意な漁師の娘よ!

昆布の佃煮、めっちゃ美味しい!噛むたびに醤油の深いコクと昆布の旨味がじわっと広がる感じがたまらないわ。食物繊維やミネラルがたっぷりなのも嬉しいのよね。とろっとした昆布の食感がクセになって、白いご飯が止まらないの。これだけでお茶漬けが何杯もいけそうだから食べすぎ注意よ。


佃煮の素材に関係する「海」や「貝」からついた名前。
バク転練習中!

貝の佃煮も大好きだけど、今の一推しは金時豆の煮豆。一粒食べると豆本来の甘さが口に 広がって、どこか懐かしくて温かい気持ちになるんだよね!食物繊維が豊富で腸活にもいいし、カリウムも多くてむくみ解消にも◎。一粒食べたらまた一粒、まさに美味しさの無限ループさ。
6月29日は「佃煮の日」について
佃煮の発祥
佃煮の名称の起こりは、江戸時代に江戸の佃島の漁師が、海が荒れ魚の獲れない時にと保存の利くように工夫して、小魚を煮込み、非常用備蓄食にしておいたものを、佃島(現在の東京都中央区)にある住吉神社を訪れる参拝客に振舞ったのが始まりで、江戸の回船問屋の主人の供で訪れた賢い奉公人が、これを佃煮の名称で売り出したのが始まりと言われております。
しかし、歴史を紐解くと、佃煮の原型は大阪にあったとみられ、時は天正10年(1582年)6月、織田信長が明智光秀の謀反によって討たれた「本能寺の変」にまで遡ります。
当時、わずかの手勢で大阪・堺に陣取っていた織田信長の盟友徳川家康は、本能寺で信長が討たれたと知って、次は己が命を狙われると身の危険を感じ、居城の三河・岡崎城に逃げ戻ろうとしましたが、既に光秀の手が回り退路を断たれ、やむなく逆方向に迂回しての脱出奇策を講じたのでした。そして家康一行が、今の大阪・住吉区の神崎川にさしかかった折、渡る船がなく足止めに遭って難渋しているとき、大阪・佃村(現在の西淀川区佃町)の庄屋「森 孫右衛門」とその配下の漁民たちが、舟とともに自身が備蓄していた小魚煮を道中食として差し出しました。日持ちが良く、体力維持にも効果を発揮した小魚煮のお陰で家康一行は、無事岡崎城に辿り着くことができました。
時が流れ、江戸幕府を開いた後も、家康は佃村漁民への恩義と小魚煮の効果を忘れず、森 孫右衛門をはじめとした漁民を江戸に移住させ手厚く加護したと伝えられており、こんな経緯から江戸での佃煮の歴史が始まったと言われております。
(資料提供/株式会社日本食品新聞社)
6月29日は「佃煮の日」のいわれ
徳川家康の招きで、江戸に移住してきた森 孫右衛門をはじめとする漁民衆は、一丸となって江戸湾の干潟の一角に築島を築き、これが1646年に完成し、これを郷里の大阪・佃村にちなみ佃島と名付けました。
そして完成したこの佃島に、郷里・佃村の産土神の御神霊を祭祁した住吉神社が建立された日が、正保2年(1646年)6月29日で、この日の「二九」を「ツク」と語呂あわせをして、2003年(平成15年)に「佃煮の日」と命名いたしました。
正式には、平成16年1月1日日付で、日本記念日協会に登録認定されています。
【参考文献】
・『水産庁編・佃煮便覧』昭和佃煮便覧刊行会(1951/5/5)
・露木英男・瀬戸貞『つくだ煮の化学と製造方法』光琳書店(1965/6/5)
・武田平八郎・全国調理食品工業協同組合『50年のあゆみ』(2005/8/17)
・「佃煮の歴史」日本食品新聞社 武田平八郎著作
・日本食糧新聞創刊70周年記念出版「食品産業時点」
・2006 食と健康に関する辞典
[お問合せ]
全国調理食品協同組合
電話 03-6807-7576